URA MAIL MAGAZINE vol.69
「ルーキー若手研究者に贈る:科研費制度150%使いこなし術」特集
本年1月23日付けで総合科学技術・イノベーション会議から「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」が公表され、国の各関連事業では、若手研究者への期待がこれまで以上に大きくなっています。科研費においても、「科研費審査システム改革2018」を経て、「若手研究」は新規採択率が40%にまで高められています。
次代の日本、世界、人類を支え、発展させることができるのは今の若手研究者ですが、彼らを取り巻く現状は、決して簡単なものではありません。
今号は、若手研究者の中でも、特に若手(科研費採択の経験がない、あるいは、初めて採択されたばかり)の研究者の方へ、との気持ちを込めてお届けします。
■INDEX
- シニア研究者へのインタビュー「科研費制度を使いこなすコツ、教えてください!」
- 科研費の動向について
- ご存知ですか?大阪大学の科研費申請支援制度いろいろ(Support for KAKENHI applications is available in English!)
- 大阪大学における新型コロナウイルス関連情報
- 大阪大学URAだより--2020年8月・9月の主な活動
- 【10/3,
10/9オンライン開催】第6回人文・社会科学系研究推進フォーラム「人社主導の学際研究プロジェクト創出を目指して~未来社会を拓く人文学・社会科学研究の現在と展望」
- 大阪大学ホットトピック
●阪大が全国唯一! 文部科学省「人文学・社会科学を軸とした学術知共創プロジェクト」に採択
●「コロナ新時代における大阪大学の取組」を作成しました
●大阪公立大学の英語名称にかかる問題点について(第4報) 〔特許庁への情報提供について〕
●SEEDSプログラムが三菱みらい育成財団2020年度「先端・異能発掘・育成プログラム」に採択されました
●研究活動上の特定不正行為に関する調査結果について
●大阪公立大学の英語名称にかかる問題点について(第3報)
●住友化学高度情報人材育成奨学金授与式が開催されました!
●「マイハンダイアプリ」を一般公開&「アプリdeオープンキャンパス」を開催します!
●大阪府からの要請も踏まえた感染拡大防止のための行動の徹底及び大阪大学活動基準(8月11日以降)
●大阪モデルにおける「イエローステージ(警戒)」の対応方針に基づく大学等への要請について
●学生の皆さんへ(総長からのメッセージ)
●「大阪大学プロフィール2020」を発行しました
●最新の研究の成果リリース
【1】シニア研究者へのインタビュー
「科研費制度を使いこなすコツ、教えてください!」
ご自身もこれまで失敗やチャレンジを重ねながら、様々な科研費研究種目の採択経験をお持ちで、科研費の制度設計あるいは審査に関わられたこともある大阪大学の先生方2名に、インタビューさせていただきました。
「当てる」のではなく「獲得する」ための調書作成術や、キャリア形成における科研費との付き合い方、若手研究者の挑戦を後押しするための制度・環境のあるべき姿など、先生方に伺った多彩な"科研費制度使いこなし術"を、メルマガ読者の方に共有します(以下は、先生方へのインタビューを再構成したものです)。
大阪大学大学院文学研究科 福永伸哉教授(専門分野:考古学)

○研究計画は"家の設計図"を描くようなもの。一本筋が通った設計図を申請書に落とし込めれば、科研費は取れる。
人文学は、基本的に、文字資料、考古資料、民俗資料、映像資料などを分析・研究する"資料学"で、資料の収集分析から出発する積み上げ式の学問です。ある日ひらめいていきなり全てが解決する、というタイプのものではないため、若い人には、まずは資料学として基礎的な部分に取り組み、手堅い成果を見込める個別テーマで小規模な研究種目へ応募することをお勧めします。審査員の立場からすると、資料分析が十分でないのに、最初から大言壮語するようなテーマや応用問題の解決を前面に出されると引いてしまうところがあります。
研究計画には、学問的な背景や気づきから導き出された解決すべき問題を「土台」として設定し、問題解決のための方法論や具体の研究作業を「柱」に成果を見通すところまで、一本筋を通すことが必要です。そういう意味で、研究計画は家の設計図と似ています。土台となる気づきが面白くても、それが柱となる方法論や作業とずれていると、家は建ちません。逆に、頭の中の設計図(=研究計画)がしっかりしていれば、それを紙の媒体に落としたものが申請書なので、採択されるはずです。申請書は理詰めの産物。時折「科研費に当たった」と耳にすることがありますが、それは適切な言い方ではないと思っています。
○新たに科研費が取れたらすぐ、次の科研費に向けた研究計画を考え始める。一つ上の研究種目に応募するつもりで構想を膨らませてから贅肉を削ぎ落とすと、緊張感のある研究計画に。
次の科研費のことはずっと考えています。新規課題が採択されたら、頭の中で設計図を描き始めますが、それをそのまま申請書にすると緩いものになってしまいます。ではどうするか、今回は特別に"企業秘密"をお話しします。私の場合は、次に応募するものより一つ上の研究種目を想定し、気づきの部分から実際の研究の内容、出てきそうな成果など、思いつくことを全て書き留めて設計図を作っていきます。このプロセスに数年かけ、応募の半年前からは実際に狙う一つ小さい研究種目に落として、内容を絞り込むのです。例えば、基盤研究(S)に応募するつもりで研究計画を考え、ものすごく絞り込んで基盤研究(A)の金額に収めると、贅肉を落として必須のものだけ残すことになるので、緊張感のある申請書になります。この方法は、約20年前、基盤研究(B)を取り始めた2001年ごろから続けています。その時は、まず基盤研究(C)のテーマを3つくらい集めた額の計画を立てて、それを削って削って基盤研究(B)の金額に収めて申請書を書きました。採択後、ある審査員の方から、申請書がよくできていたと評価いただいたことを覚えています。
その他、魅力的な申請書を作成する上で力を入れるべきは、何と言っても題目(研究課題名)と最初の10行です。審査員は一人当たり最大150件ほどの申請書を読んで相対評価していきますので、ここで引っかからなければ弾かれてしまいます。特に題目は、申請書作成の労力の10%をかけるに値します。究極的にはセンスの問題になってきますが、科学研究費助成事業データベースで同じ研究種目/研究分野の過去の採択課題をチェックして考える方法も有効でしょう。考古学の場合、古墳時代の研究層は厚いので、題目に「古墳時代」を入れると陳腐に見えてしまう恐れがあります。あくまで一例ですが、「古墳時代」を「国家形成期」などの別の言い方に変えることで、新しい研究であることを伝えるのも一案です。世渡りの術として、研究を魅力的に見せるための申請書作成の技術を磨いていっていただくと良いと思います。
○地道な研究とギャンブル的な研究の両方を並行して進める。常にアンテナを張っていると、いい研究テーマが見つかり、研究者として化ける可能性が高まる。
考古学は、お金が無いとフィールド調査も学生教育もできないという事情があるため、基盤研究種目への申請では失敗が許されません。また、何年かに一度、測量機器や顕微鏡など高額な機器が必要になるため、特にその時には大型研究種目を取りに行きます。他方、重複応募のできる挑戦的萌芽研究(現「挑戦的研究」)については、いわばギャンブル的に捉えて、工学系の先生などとの学際的な研究を楽しむために活用するなどにしています。世知辛い世の中における研究者としてのキャリア形成を考えると、これまでの積み上げによりコンスタントに論文が書けるテーマを1つキープしつつ、新たなテーマを発掘するギャンブル的な研究も並行してやっていく必要があると思います。ギャンブルがうまくいくと、先駆者になれるからです。
"研究者として化ける"には、良い研究テーマとの出会いが必要です。私自身、当初は平凡なテーマで研究に取り組んでいましたが、20代の終盤、邪馬台国論争にも関係する三角縁神獣鏡の小さな紐孔の形の違いを発見し、その違いを手掛かりに三角縁神獣鏡の製作地という大きな謎に挑むことになります。その後しばらくは、科研費などを使って日本や中国、朝鮮半島に調査に出かけ、数千枚の鏡を見て回り、研究を大きく発展させたことで、古墳時代の専門家としての道が拓けました。この過程で、私もある意味"研究者として化けた"と自負していますが、これは、研究者としての能力よりも、常にアンテナを張っていたことがもたらした気づきによるものだと思います。科研費申請に関しても、良いテーマを見つけるために常にアンテナを張って受信状態におくことをお勧めします。
○資金配分制度にひとこと:若手への門戸の更なる拡大、科研費と組み合わせられる資金の多様化を
科研費の制度改革は進んでいますが、若手研究者の採択率を60〜70%くらいまで上げてはどうか思います。特に人文学の場合は、年に70〜80万円あれば、基礎的調査で成果が出せます。エントリーレベルの若手研究者が一気に階段を3段、4段上がるのは無理なので、まずは一段ずつ上っていけるような、薄く広い支援が効果的です。また、同じく若手関連で言うと、新たに立ち上がった研究種目の学術変革領域研究は、それが有効に活用されば、違うテーマを結合して役割分担しながら進める研究の経験を通じて、将来研究グループを引っ張っていく研究者を育てられるものと期待しています。
最後に、科研費を含む資金配分制度の多様化についてお話しさせてください。多くの分野の研究者は、運営費交付金と科研費に様々な資金を組み合わせながら、継続的に研究を発展させようとしているはずです。いま、国の重要政策の一つに「文化芸術立国の推進」があります。これを受けて文化庁ではアートマネジメントの人材育成のために「大学における文化芸術推進事業」という補助金制度を作っていて、阪大でも文学研究科の芸術系教員が中心となって今年度1件採択されています。残念ながら私の関係する文化財分野では、「観光立国戦略」がやっと始まったところでまだ大学連携事業がなく、文化庁の方にぜひ作ってほしいと申し上げているところです。これはあくまで一例ですが、日本の将来のために、また科研費の成果を人材育成や地域社会の振興等と結びつけるためにも、より多様で効果的な資金投入を検討いただきたいと思います。コストパフォーマンスの点では人文系は強いですからね。
大阪大学核物理研究センター 中野貴志センター長・教授(専門:物理学)
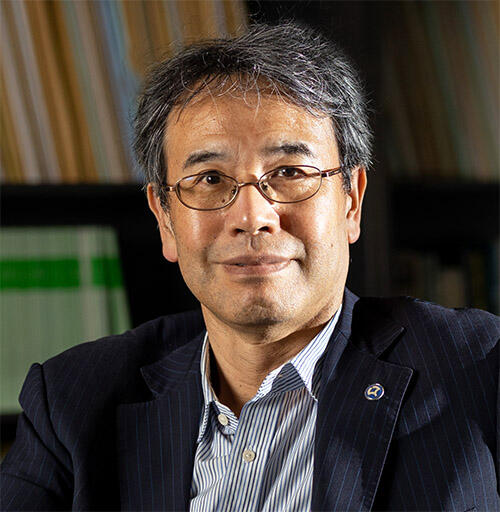
○若手にとってまず"一発目"を通すことが大事だが、それは簡単ではない。どうすればよい?
若手にとってはとにかく"一発目"を通す、というのが大事です。科研費は、大きくは、若手研究という若手枠と基盤研究などの一般枠があり、まず、採択率の高い若手枠でしっかりと採択を目指しましょう。
何故かと言うと、直近の「科研費審査システム改革2018」(以下、「科研費改革」という。)後の制度改善により、若手枠に採択された研究者にも審査員をしてもらうことになったためです。採択されると、審査員候補者データベースに登録され、そこに自身の情報をきっちり入力しておくと、審査員に選ばれる可能性が高まります。その際、担当できる分野も広めに登録しておくと良いでしょう。審査員を経験すると、様々、得られるところがあるので、早期に審査員を経験してほしいと思います。
科研費の審査員を経験する意義は2つあります。一つは、研究者としての義務を果たす、ということです。科研費が生かされるかは、公平性・公正性の観点で研究者が適切に審査をすることにかかっています。良い研究課題を選ぶ目利きも重要です。科研費をより良い研究費制度として維持、発展させていくためには、研究者コミュニティ全体で取り組まなければなりません。もう一つは、研究計画調書(以下、「調書」という。)を、良い例も悪い例も、大量に読めるということです。もちろん守秘義務はありますが、特に、悪い例をたくさん見ることは、確実に自らの調書作成のレベルを上げることにつながると思います。自らの失敗のみならず、他の方の失敗から学ぶことは多いのです。事務部門の担当者やURAは、採択者の調書を見ることが多いかもしれませんが、調書作成支援をするためには、それだけでは十分でない可能性があります。
冒頭、"一発目"を通すと言いましたが、これは言うほど簡単ではなく、できるだけたくさんの様々な方の調書を読むことも難しい場合があります。そんな時は、審査員経験があり、採択経験も多い研究者に作成した調書を読んでもらうことが大事になります。その際、可能ならば、自身とできる限り離れた異なる専門分野の研究者に見てもらい、そのような人にもわかってもらえる調書に仕上げると良いでしょう。また、他の研究者とお互いに批判的に調書を読み合うのもお勧めです。URAには、このような異なる専門分野の研究者間をつなぐ役割を期待します。
○新たな研究が本来持つ面白さが伝わるような、審査員も喜ぶ「良い調書」に
昨今の「科研費改革」等を経て、特に大型支援金額の研究種目を中心に、以前よりも様々な専門分野をもつ審査員による審査が広がりつつあります。それに伴い、申請者から大きく離れる専門分野の審査員も積極的に意見を出す審査になってきています。このような審査においては、より一般的で、分野を超えた説得力をもつ調書が必要となります。審査員は皆知的レベルの高い人たちで、何とか申請書の良いところを見逃さないようにと真摯に審査していますから、「どうせ専門外の審査員にはわからないだろう」と考えて調書を書くのは間違いです。
審査員として調書を見ていると、自身とは異なる専門分野の研究者の違う考え方、アプローチなどに学ぶことがあります。こういう時は、「得した!」と思います。「自身の学問の幅が広がった」とも感じます。このような"得したと思う調書"は決して多くはありませんが、申請者は、審査員にそう思ってもらえるような調書を書いてほしいものです。大型金額の研究種目が対象になるヒアリングに行った際に「分野の近い人がいた、いない、審査員が誰だった」ということを言う人がいますが、これらは小さなファクターでしかありません。また、「科研費が当たった、当たらない」というのは、表現として適切でなく、このように言っているうちは、なかなか採択されないのではないでしょうか。審査員になって良かったと思える「良い調書」は、様々な専門分野の審査員による審査でも評価が割れることはありません。
科研費は、新しい研究を申請するものなので、基本的に、本来面白い内容のはずです。面白くない調書やヒアリングでのプレゼンは、この面白さのポイントがうまく表現できていないのだと思います。より「良い調書」にしていく過程で、申請者自身も気づいていない、うまく言語化されていなかったようなポイントやものの見方を明らかに表現できると、誰が見ても面白い調書になります。これは、調書作成を手伝った人にも「あ、なるほど!」という気づきを与えます。審査員側としては、このような本来面白い研究が書かれている調書をわかる楽しさ、というものもあります。ただし、調書の1ページ目で「あ、面白い!」 と思わせなければなりません。1ページ目でポイントがぼんやりしていると、その印象の下、それ以降のページを読んでいくことになってしまいます。
○科研費による若手研究者の挑戦を最大限に活かすために必要な環境整備
科研費での現在の戦略的な若手支援の方向性は、挑戦的でエースとなるPI、研究室を主宰できる研究者を育てる、増やしていくことを目的としています。厳しい言い方かもしれませんが、全ての若手の支援を目指しているわけではない点には注意しないといけません。他方、若手研究者に科研費で挑戦的な研究をしてもらうための最大の環境整備とは、やはり職を安定させることです。職の安定がないと日銭を稼ぐことに追われ、真の挑戦は困難です。デュアルサポートシステム(※)の片翼を担う大学・研究機関側が職の安定を担保し、若手が歯車としてではなく、じっくりと面白いことを考えて挑戦する研究に科研費を充てられるようする必要があります。
環境整備に関し、そのデュアルサポートシステムが崩れかけているのが、日本の最大の問題です。崩れかけている結果として、採択がより確実と思われる研究種目、例えば基盤研究(C)へ申請が集中する傾向が見られたり、本来は研究者の自発的な行動であるべき科研費申請を組織として義務付けるところが増えたりしています。そもそも自前で準備すべき基盤的な予算を科研費に頼っているということでは、科研費本来の「挑戦する」という方向とは逆の方向に進んでしまい、科研費が活きなくなります。
科研費をより活かすためには、「科研費改革」だけでは収まらないと感じています。私が臨時委員として参画する研究費部会でも、今回、文部科学省内の科研費以外の資金配分制度を所掌している部署や様々な研究・開発事業を展開している科学技術振興機構(JST)等と、若手支援について話し合いました。その結果、今後、これまで以上に縦割りを廃し、若手研究者の国際的なプレゼンス、競争力を高めていくための総合的な支援に取り組むことで合意されています。自身の明確な研究者としてのキャリパスやビジョンをもって科研費を活用していくことは、他の制度の支援を受けることへもつながっていくでしょう。
また、若手研究者が挑戦できる環境を整える上では、年度内予算使用などの縛りのない資金として使用できる基金などを、できる限り多く確保していく必要があります。これを大学の中につくるのか・外につくるのかいう議論はさておき、今の大学ではサポートできないところに対応できる基金があるのが望ましいと思います。私自身は、昨年8月、核物理研究センターを中心とした研究成果を社会に届けていくための一般社団法人を新たに設立しました。ゆくゆくは、企業等と密接な関係を築きつつ、大学の研究を支えるべく、持続的に運営していきたいと考えています。
○最後に:科研費に関する若手研究者へのメッセージ
大阪大学は、各専門分野間や部局間の敷居が低く、やりやすいと感じています。実際、医学系などの研究者等とも連携し、一緒に仕事をしてきました。新しいプロジェクトを立ち上げるのに、新たに異分野の方々と出会い、アイディアを磨き合いながら進んでいくというのは、科研費への申請におけるアプローチと変わりません。自分一人では決して思いつかないアイディアや実行できない解決法の創出といったものが、分野や自らが所属する部局、大学を超えることで可能になっていきます。科研費というあらゆる分野を対象としたところで、多様な意見を審査員として読むことをしないと、「良い調書」にたどり着けないのにも通じるかもしれません。他(多)分野の研究者等と交わり、磨き合うことが何より大事だと思っています。
※ デュアルサポートシステム: 我が国の大学等においては、基盤的経費の確実な措置と、競争的資金との有効な組み合わせ(デュアルサポートシステム)によって研究体制を構築。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/attach/1337896.htm
【2】科研費の動向について
昭和43年に開始した科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)は、人文学、社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピアレビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。
平成30年度採択分より、新たな審査区分および審査方式の導入を中心とした抜本的な見直し、いわゆる「科研費審査システム改革2018(科研費改革2018)」が実施され、大幅な変革がありました。
本稿では、文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会第10期研究費部会(以下「研究費部会」という。)での議論等を踏まえ、令和3 (2021) 年度科研費の公募に係る制度改善等のうち、特に若手研究者支援に関係するものをご紹介します。
1. 研究費部会「第6期科学技術基本計画に向けた科研費の改善・充実について(中間まとめ)」に基づくもの
○「若手研究」の研究期間の延伸
令和3 (2021) 年度科研費の公募より、若手研究者が継続的・安定的に研究を遂行できるように、「若手研究」の研究期間を「2〜4年間」から「2〜5年間」に延伸することが予定されています。
研究期間の延伸は、これまで以上に継続的・安定的な研究実施を可能とするために行われるものであり、研究期間の上限を5年間とすることで単年度当たりの研究費が減額されることがないように、充足率の向上を併せて行うべきである、という議論が研究費部会でされています。他方、「若手研究」種目群への応募については、その趣旨が経験の浅い若手研究者に研究費を得る機会を与え研究者として良いスタートを切れるように支援することであるとともに、「若手研究」種目群から「基盤研究」種目群へのスムーズな移行を励行するため、一度「基盤研究」種目群に採択された者については「若手研究」への応募を認めない方向で応募制限を見直すことが適当と考えられる、といった意見も出されています。
○国際共同研究加速基金「帰国発展研究」における応募資格の変更
本制度は、海外の研究機関等において独立した研究者を対象としていることから、従来、応募資格を応募時点において「日本国外の研究機関に教授、准教授又はそれに準ずる身分(ポストドクターを除く)」を有していることとしていました。他方、ポストドクターの中には自らの責任で自由に使用できる研究費を獲得している場合などもあるため、「独立した研究者」や「ポストドクター」についてすべての研究分野において合意を得られるような明確な基準等を設けることは困難でした。
そもそも本種目は、海外で活躍した日本人研究者が、帰国後に外国人研究者との連携等により日本の研究活動の活性化に資することや、帰国直後の研究費支援があることで若手研究者の海外挑戦の後押しにつながることが期待されています。海外で活躍する優秀な若手研究者の応募機会をさらに拡大するためには、本種目の趣旨に合致している者であれば「ポストドクター」という身分であったとしても、本種目への応募を認めることが適当である、との議論が研究費部会でなされました。そして、本年9月1日公募開始の令和3 (2021) 年度公募より、「ポストドクター」という身分であっても本種目の趣旨に合致する場合には応募可能となりました。
2. 総合科学技術・イノベーション会議 (CSTI) 「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」(令和2年1月23日)等に基づくもの
○研究以外の業務の代行に係る経費の支出が可能に
「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年5月22日文部科学省研究振興局、科学技術・学術政策局、研究開発局、高等教育局申し合わせ)を踏まえ、科研費においても令和3 (2021) 年度から研究代表者および研究分担者の研究以外の業務の代行に係る経費の支出が可能となります。
バイアウト制度とは研究代表者本人の希望により研究機関と合意をすることで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務の代行に係る経費の支出を可能とする制度です。資金配分機関の判断において、研究分担者も同様にバイアウト経費の支出を可能とすることは差し支えないとされています。研究機関においては、業務の代行に関するしくみを構築し、代行させる業務内容と必要な経費等について研究機関と合意し、代行要員を確保する等により業務の代行を実施することができます(※)。
○科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施が可能に
「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)を踏まえ、令和2 (2020) 年4月から、科研費により雇用される若手研究者が一定の条件の下、雇用元の科研費の業務に充てるべき勤務時間において自発的な研究活動等の実施を可能としています。
競争的研究費で雇用されている若手研究者は、当該プロジェクトに従事し、他の研究活動を実施する場合には、当該プロジェクト以外の雇用財源を確保することが必要となりますが、他からの財源が確保できない場合があり、一部の実施のみにとどまっているという現状があります。そこで、若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成のため、競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される一定の要件を満たす若手研究者について、雇用されているプロジェクトから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を、プロジェクトの推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動に充当することが可能となりました(※)。
※上記2つの制度変更を受けた本学の対応については、現在検討が進められています。
科研費改革2018の影響により、平成30年度採択分から科研費の審査体制等のしくみが大きく変化しましたが、改革後も引き続き、さまざまな検討や変更がなされています。本学において研究支援業務を行っている当部門においても、今後も科研費の動向に注目していきたいと考えています。
【主な参考資料】
令和3 (2021) 年度科学研究費助成事業(科研費)の公募に係る制度改善等について
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_200812/index.html
第6期科学技術基本計画に向けた科研費の改善・充実について(中間まとめ)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/045/1413368_00002.htm
研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000033155.pdf
競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/torikumi/1385716_00003.htm
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/torikumi/1385716_00001.htm
【3】ご存知ですか?大阪大学の科研費申請支援制度いろいろ(Support for KAKENHI applications is available in English!)
協力:大阪大学 研究推進部 研究推進課 学術研究推進係)
今年も科研費の公募が始まりました。
以下は、日本語・英語での相談員制度や「外国人研究者向け科研費説明会」など、大阪大学の科研費申請に関する支援制度(全て学内向け)です。
本学教職員の皆さんは、ぜひ一度詳しい情報をご確認ください。
| No. | 名称 | 主な対象 (全て学内向け) |
時期(2020年) | 概要 |
| ① | 科学研究費助成事業学内説明会(日本語) | 科研費申請を予定している研究者、科研費担当職員 | 新型コロナウィルスの影響のため、現在、検討調整中 | 科研費制度の概要、科研費不正使用防止等についての説明。 |
| ② | 外国人研究者向け科研費説明会(英語) KAKENHI Information Session for International Researchers (in English) |
本学の外国人研究者およびその支援者 International researchers in Osaka University and support staff |
新型コロナウィルスの影響のため、現在、検討調整中 | 外国人研究者向けの科研費制度の概要説明およびアドバイス。 This Information session provides outline of the KAKENHI and suitable advice for applicants. 【Ref.】KAKENHI Information Session of FY2020's (Login to My Handai is required)  |
| ③ | Application Manual for the Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) Program FY2021 edition | 外国人研究者およびその支援者 OU International Researchers and their supporters |
9月中旬ごろ公開 Available from Mid-September |
外国人研究者およびその支援者向け、科研費英語申請のためのコンテンツ。 This manual provides a lot of useful information on the KAKENHI for international researchers. 【Ref.】Application Manual for FY2021 Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) (Login to My Handai is required) |
| ④ | 科研費研究計画調書作成セミナー(日本語) | 本学に所属する教員で、主に初めての科研費採択を目指す若手研究者(令和2年度科学研究費助成事業若手研究、基盤研究(C)の応募予定者) | 新型コロナウィルスの影響のため、現在、検討調整中 | 科研費相談員による、科研費研究計画調書の作成に対する考え方、応募の経験並びに審査の視点を踏まえた分野ごとの講義。希望者にはURA部門URAによる個別アドバイス。 |
| ⑤ | 科研費相談員制度(日本語・英語) Advisory System(Jp/En) |
本学から申請を予定している研究者で、本制度利用時点で本学に科研費応募資格がある者 Researchers who are eligible to apply for FY 2021 KAKENHI from Osaka University |
9月中に開始予定 Available from Mid-September |
科研費制度に精通した相談員による、研究計画調書に対するアドバイス。 別に案内予定 The applicants, such as young and core researchers, are able to consult with professors who are familiar with KAKENHI and the applicants' research field(s). To be announced. |
| ⑥ | 研究計画調書の事務チェック | 本学から申請を予定している研究者のうち希望者 | 受付 10月2日~10月9日 | 研究計画調書が所定の様式を使用して作成されているか等の、書面チェックを行います。 |
| ⑦ | 模擬ヒアリング | 基盤研究(S)、特別推進研究、学術変革領域研究(A)のヒアリング審査対象者 | ヒアリングの時期に応じて個別調整 | 大阪大学における競争的資金獲得増加のため、大型プロジェクトの審査等に対応した模擬ヒアリング・模擬面接を実施し、採択率向上を図るもの。大型科研費の他、日本学術振興会特別研究員等の面接・ヒアリング審査にも対応。 【参考】大阪大学経営企画オフィス研究支援部門(URA)ウェブページ |
| 参考 | 科研費による論文等の成果発表者 | 通年 | 研究者使用ルールに【研究成果発表における表示義務】の記載があります。ここでは、「研究代表者及び研究分担者は、補助事業の成果を発表する場合には、助成金の交付を受けて行った研究の成果であることを表示しなければならない。特に、論文等により補助事業の成果を発表する場合には、論文等の謝辞に助成金の交付を受けて行った研究の成果であることを必ず記載しなければならない(「JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号」を含めること。)。」とあり、改めてのご確認をよろしくお願いいたします。 |
【問い合わせ先 Contact】
①〜⑥:大阪大学 研究推進部 研究推進課 学術研究推進係
Research Promotion Division, Department of Research Promotion, Osaka University
TEL:06-6879-7033
E-mail:kensui-kensui-gakuzyutu@office.osaka-u.ac.jp
⑦:大阪大学 経営企画オフィス URA部門
Research Management and Administration Section, Office of Management and Planning, Osaka University
内線:06-6879-4981
E-mail:ou-mogi@lserp.osaka-u.ac.jp
※上記以外、各部局独自の支援制度を設けている場合があります。詳しくは各部局の担当部署にご確認ください。
【4】大阪大学における新型コロナウイルス対応関連情報
●大阪大学公式サイト「新型コロナウイルスへの対応について」
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona
大阪大学の活動基準、コロナウィルスに関連した取組・研究成果等がまとめて紹介されています。
●「コロナ新時代における大阪大学の取組」を作成しました
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2020/08/20200828001
新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界はコロナ新時代と呼ばれる難局を迎えており、社会のあらゆる面で、これまでの常識からの変革が必要となっています。
本学では、コロナ新時代を迎えるにあたり、教育、研究、産学共創・社学共創、国際、働き方改革に関し、どのようなビジョンのもとで大学を経営し、活動を展開していくのかについて、「コロナ新時代における大阪大学の取組」として、2020年7月末時点での概要をとりまとめました。
●コURA部門サイト「コロナ禍に関連する研究教育活動の特設ページ」をアップデートしました
https://www.ura.osaka-u.ac.jp/researchersupport/2020428.html
主に人文社会科学系部局のコロナ禍に関連する取組の情報を追加しました。
【5】大阪大学URAだより--2020年8月・9月の主な活動
●外部資金獲得支援いろいろ
・科研費 学術変革領域研究(A)模擬ヒアリング
・FY 2020外国人研究者のための科研費申請マニュアル作成
・JST戦略的創造研究推進事業模擬面接
・JST共創の場形成支援プログラム申請支援
●学内支援プログラムを運営・支援しています
・2020年度論文作成・発信支援
https://www.ura.osaka-u.ac.jp/researchdissemination/2020support_for_accessing_publishing_academic_papers.html
・教員等「公募要領(英語・日本語)作成支援ツール」の配付をしています
https://www.ura.osaka-u.ac.jp/international/post_12.html
●その他
・本部と部局の研究推進・支援業務担当者の情報共有や意見交換のためにURAミーティングを定例開催(2週間に1回)
・研究力強化施策の検討サポート
・部局の研究力分析へのコンサルテーション
・事務改革提案チームへの支援
・先導的学際研究機構の活動支援
・各種学内会議・委員会への参画
【6】【10/3,10/9オンライン開催】第6回人文・社会科学系研究推進フォーラム「人社主導の学際研究プロジェクト創出を目指して~未来社会を拓く人文学・社会科学研究の現在と展望」
※大阪大学経営企画オフィスURA部門も共催しています。
文理融合・異分野融合/連携など様々に表現される学際研究ですが、近年、人文学・社会科学の視点を盛り込むことが重要視されています。しかし現状では、理系(自然科学)主導のプロジェクト内のごく一部に人社系研究者が関与する形が主流と言わざるを得ません。アカデミアに対して研究成果の社会還元が期待される今、人文学・社会科学がアカデミア全体の中で果たす役割はさらに増大すると考えられます。
そこで今回のフォーラムでは、昨今の動向と問題意識を共有し、様々なタイプの異分野融合/連携の事例を参考に意見交換を行い、さらなる人社主導のプロジェクト創出について議論を深めたいと思います。
なお、このフォーラムは、2020年2月26日に予定していましたが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、延期としておりましたものです。この度、オンライン開催にて2日間に日程を分けて、開催させていただきます。
【日程】
<講 演>
2020年10月3日(土) 午後14:00~17:30(受付開始 13:30~)
-定員:300名 / 要事前申込・先着順-
・開会挨拶・来賓挨拶・趣旨説明:14:00~14:15
・基調講演(第1部): 14:15~15:15
・事例紹介(第2部): 15:30~17:25
・閉会挨拶: 17:25~
<ワークショップ>
2020年10月9日(金) 午後15:00~17:00(受付開始 14:30~)
-定員:80名 / 要事前申込・先着順-
※ワークショップは、10/3(土)開催の講演会(第1部・第2部)を聴講された方の参加を想定しております。
【会 場】
オンライン開催(Zoomを予定)
【対象者】
研究者、URA等大学・研究機関職員、省庁関係者、助成団体関係者等
【参加費】
両日とも無料
【プログラム詳細】
https://www.ura.osaka-u.ac.jp/ssh/20200825.html
【参加申込】
以下のURLをクリックすると、申込フォームへジャンプします
https://forms.gle/1eHGFg4bUsyLrCgm9
※申込締切:定員になり次第
【主 催】
北海道大学 大学力強化推進本部 研究推進ハブURAステーション
【共 催】
大阪大学 経営企画オフィスURA部門
京都大学 学術研究支援室(KURA)
筑波大学 URA 研究戦略推進室/ICR
早稲田大学 リサーチイノベーションセンター 研究戦略部門
琉球大学 研究推進機構研究企画室、横浜国立大学 研究推進機構
中央大学 研究支援室
【お問い合わせ先】
北海道大学 大学力強化推進本部 研究推進ハブ URAステーション(担当:中野・加藤)
TEL:011-706-9577・9596(内線:9577・9596)
E-mail:ura-seminar[at]cris.hokudai.ac.jp
※[at]を半角@に変えてお送りください。
【7】大阪大学ホットトピック
●阪大が全国唯一! 文部科学省「人文学・社会科学を軸とした学術知共創プロジェクト」に採択
●「コロナ新時代における大阪大学の取組」を作成しました
●大阪公立大学の英語名称にかかる問題点について(第4報) 〔特許庁への情報提供について〕
●SEEDSプログラムが三菱みらい育成財団2020年度「先端・異能発掘・育成プログラム」に採択されました
●研究活動上の特定不正行為に関する調査結果について
●大阪公立大学の英語名称にかかる問題点について(第3報)
●住友化学高度情報人材育成奨学金授与式が開催されました!
●「マイハンダイアプリ」を一般公開&「アプリdeオープンキャンパス」を開催します!
●大阪府からの要請も踏まえた感染拡大防止のための行動の徹底及び大阪大学活動基準(8月11日以降)
●大阪モデルにおける「イエローステージ(警戒)」の対応方針に基づく大学等への要請について
●学生の皆さんへ(総長からのメッセージ)
●「大阪大学プロフィール2020」を発行しました
- 2020年9月2日
デスクワークの男性は蛋白尿のリスクが高い可能性が明らかに
大阪大学職員10,212人の定期健康診断データを用いた疫学研究 - 2020年8月31日
相対論的磁気リコネクションの地上実験に成功
ブラックホール周囲からの X 線放射のメカニズム候補を実験室で検証 - 2020年8月28日
筋萎縮性側索硬化症(ALS)を引き起こすタンパク質の新機能を発見
新たな治療法開発に期待 - 2020年8月27日
X線からガンマ線まで1台で同時に可視化できる装置を考案
医療分野の新たな診断や宇宙観測にまで応用可能 - 2020年8月27日
神経変性疾患を引き起こす異常伸長リピートRNA が分解される仕組みが明らかに
前頭側頭葉変性症と筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病態解明への確かな一歩 - 2020年8月27日
人工膜タンパク質で世界で初めての成果 ナノサイズの細孔を有する人工膜タンパク質を設計 その機能・構造を明らかに
バイオセンサーなどバイオテクノロジー分野への応用に期待 - 2020年8月26日
あっという間に傷が回復
強靭でリサイクル可能な自己修復性超分子材料 - 2020年8月26日
シリコンを黒鉛シートで包んだ構造を発見!
シリコンを黒鉛シートで包んだ構造を発見! - 2020年8月24日
新型コロナウイルス感染性肺炎の重症化抑制の仕組みを解明
IL-6 を抑えて血管障害因子の産生を抑制する - 2020年8月22日
原子層超伝導体に振動外場を加えて負の抵抗が実現
新しい超伝導デバイスへの道 - 2020年8月21日
ゼロエネルギーで運動する磁極粒子の回路
AIの超低消費電力化に向けた基盤技術の実現 - 2020年8月21日
30秒ごとに更新するゲリラ豪雨予報
首都圏でのリアルタイム実証実験を開始 - 2020年8月21日
溶液に浸すだけで結晶内に金属クラスターを形成
イオン固体を反応場とする新合成技術 - 2020年8月20日
なぜ老化は生活習慣病を引き起こすのか?
オートファジー阻害による新規治療戦略 - 2020年8月20日
新たに発見された層状ニッケル酸化物超伝導体の電子状態を数値シミュレーションにより解明!
高温超伝導を示す新物質探索のヒントになる可能性も! - 2020年8月19日
湿度によって色が変わる新しい分子性多孔質結晶を開発 - 2020年8月17日
地震時に断層でセラミックスが作られる!?
焼結した岩石が断層強度回復や地震エネルギーに与える影響の解明 - 2020年8月8日
日本人の家族性膵臓がん関連遺伝子を解明
膵臓がん克服に向けて前進 - 2020年8月1日
関節リウマチにおける間質性肺炎リスク遺伝子領域の同定
肺線維化に関わる胸部CT画像パターンと関連 - 2020年7月31日
機械学習で実現。市販の機器で高精度食品分析を可能に。
IoT 時代のビッグデータを低コストで分析できる技術 - 2020年7月30日
「癌ケトン食治療コンソーシアム」研究成果 進行性がん患者で新しいケトン食療法による有望な結果
国際科学雑誌Nutrientsで発表 - 2020年7月29日
アルツハイマー病の原因物質を「毒性」に変貌させる 新しいメカニズムを発見
溶けているはずの塩がナノレベルでは析出と溶解を繰り返すことが原因 - 2020年7月28日
転移リンパ節が予後を決める!
食道がん抗がん剤治療の新たな病理効果判定法を確立 - 2020年7月28日
神経細胞の発達の鍵はタンパク質のアルギニンメチル化修飾にあり!
指定難病の脊髄小脳変性症の発症メカニズム解明に期待 - 2020年7月23日
"光生検"切らずにその場でがんをすぐ診断
イメージングで組織を傷つけずに立体観察、AIが自動診断
メールマガジンのバックナンバー一覧はこちら。
INDEXに戻る
【企画・編集・配信】
大阪大学経営企画オフィスURA部門(旧 研究支援部門)
担当:佐藤・川人◎配信停止やご意見・ご感想はこちらまで
http://osku.jp/v0842〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1共創イノベーション棟 401
http://www.ura.osaka-u.ac.jp/2021年3月 2日(火) 更新
ページ担当者:佐藤、川人



